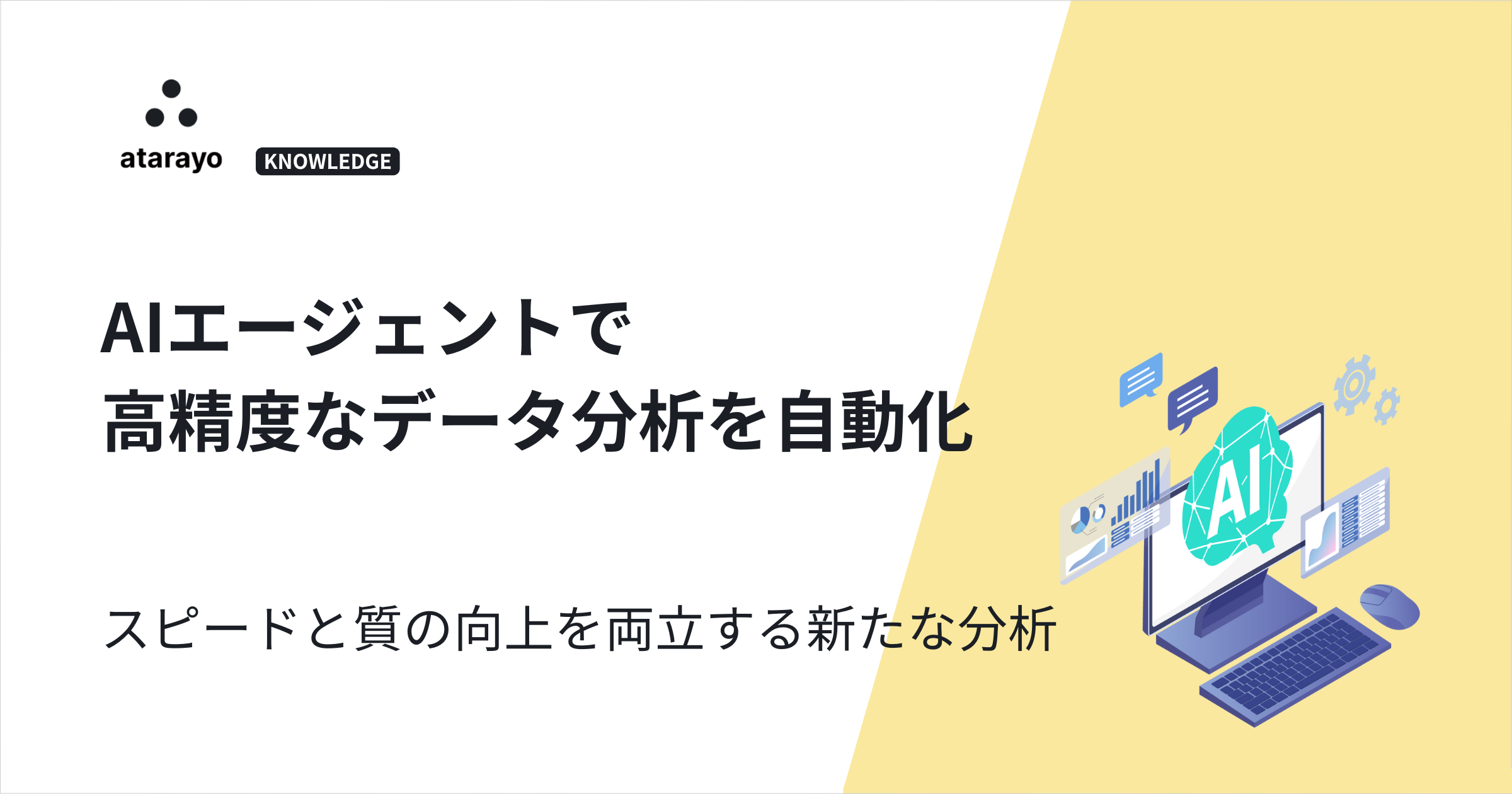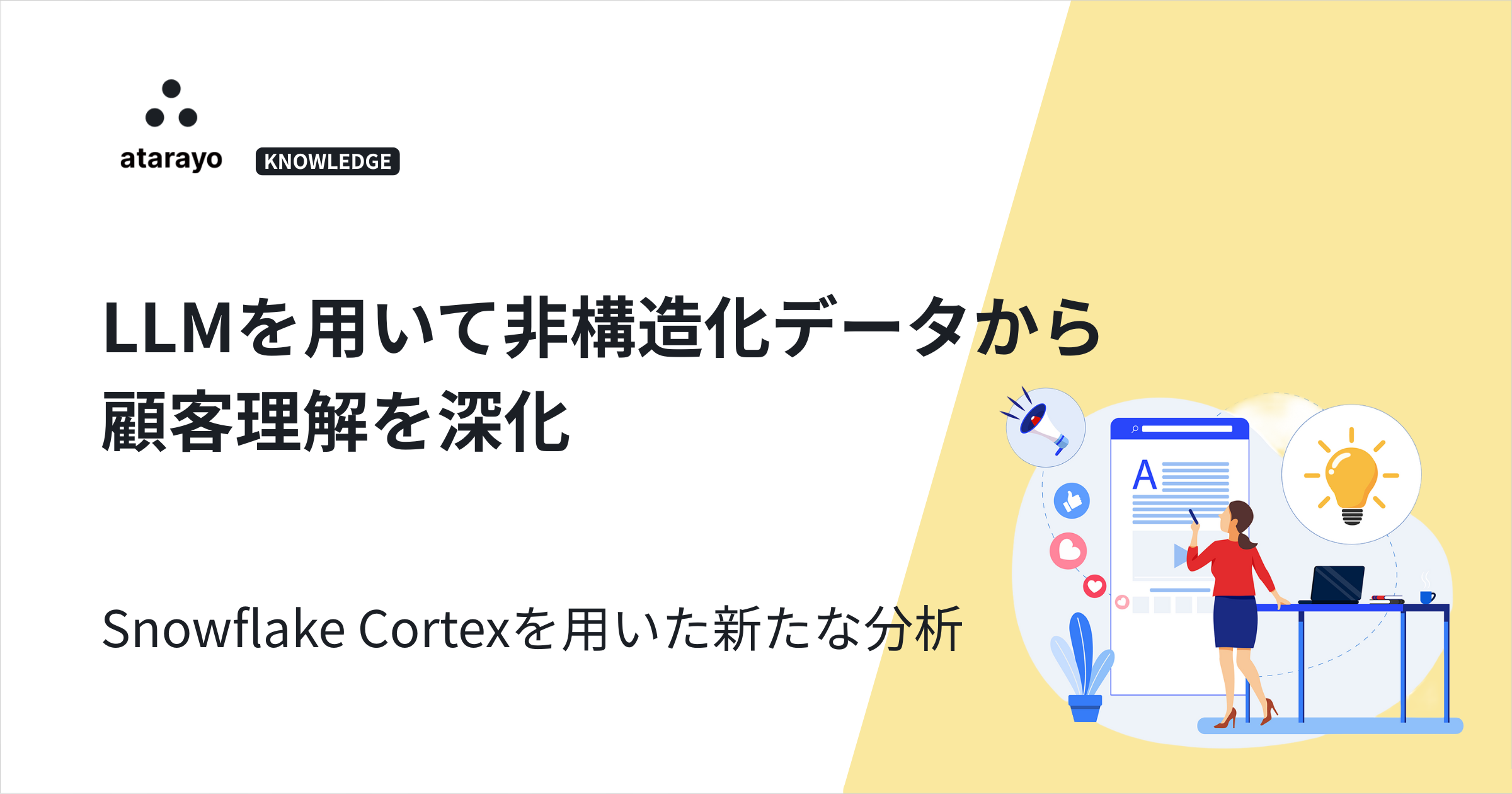【DX推進】何から、どう進める?|実践ステップとポイント・事例までを解説
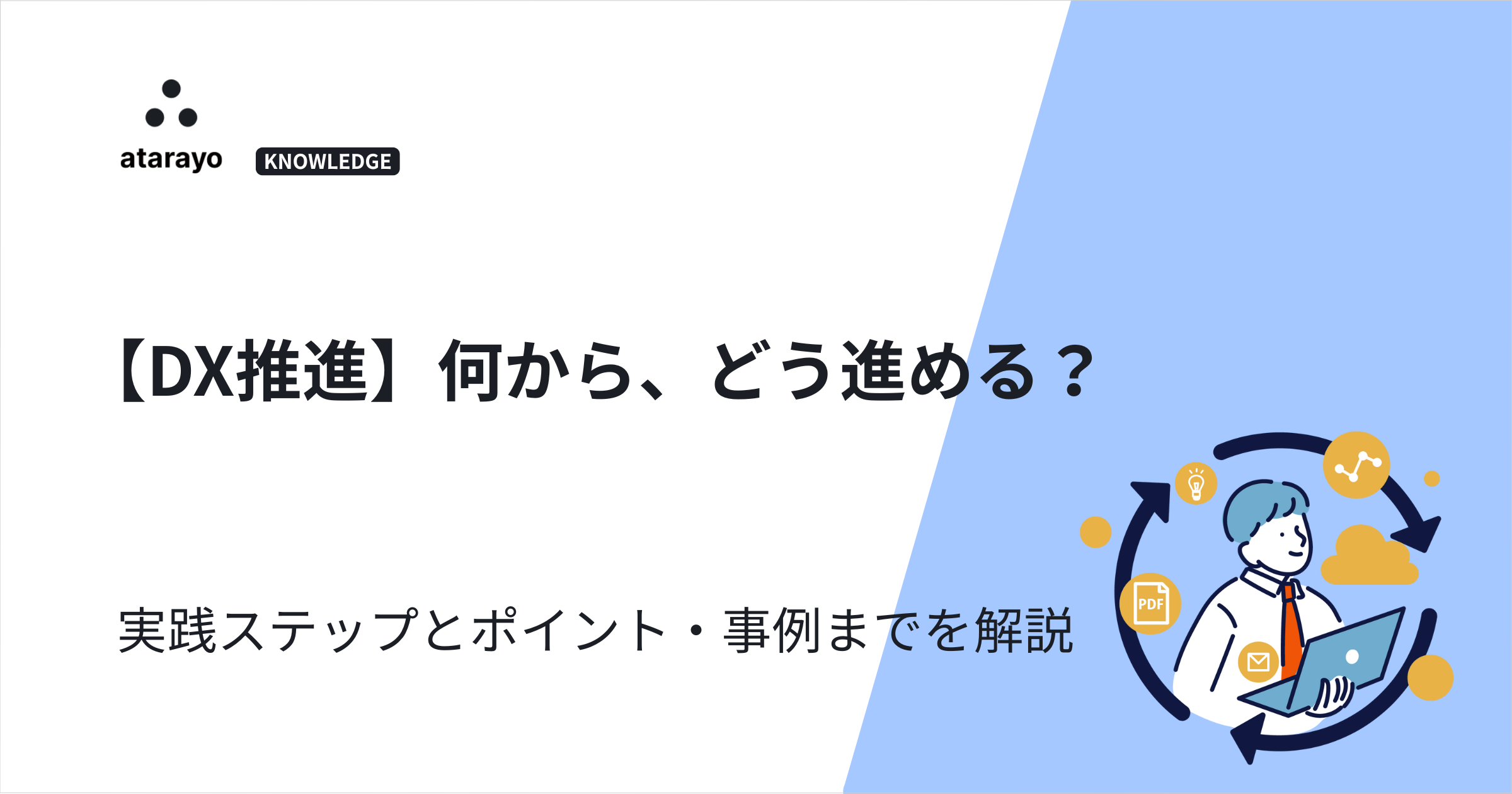
少子高齢化、デジタル技術の爆発的な進化、消費者行動の多様化、パンデミックなどの予期せぬ危機、、日本企業は激しい変化に直面しています。また「2025年の崖」として警鐘が鳴らされるように、旧態依然としたレガシーシステムは年間最大12兆円の経済損失リスクを突きつけています。
また、AIを活用してビジネスで優位性を築くには、独自のノウハウや情報を蓄積したデータ基盤が重要になります。というのも、AIの学習する情報は、独自性が高く価値が大きいほど、AIのアウトプット品質も高くなるからです。そのため、AIの価値を最大化するためにも、前段としてDXが必要不可欠なのです。
もはや、DXそしてAX(AIトランスフォーメーション)とは「やったほうがいいこと」ではなく、「やらなければ生き残れない」時代の必須戦略となっています。
このような状況下でDX推進は、データドリブンな意思決定による新たな価値創出と顧客体験の向上、AIによる業務の劇的な効率化と人手不足解消、パンデミックや災害などの有事への対応力強化など、多くのメリットをもたらします。 しかし、闇雲なDX推進では、期待する効果には繋がりにくいため、しっかりとしたステップを踏んでいくことが重要です。
この記事では、実践的なDX推進ステップ、ポイント・注意点、実際のDX事例をご紹介し、丁寧に解説します。
DX推進のステップ
DX推進は一朝一夕で成し遂げられるものではなく、段階を踏んで着実に進めることが成功の鍵となります。ここでは、DX推進の主要なステップを解説します。
ステップ1:現状のデータ活用課題の特定と要件定義
DX推進の第一歩は、漠然としたビジョンを掲げるのではなく、「データをどのように活用して顧客への価値に繋げるか」や「データをどのように活用して現状の課題を解決したいか」を明確にすることです。これにより、データ活用の具体的な要件を定義し、DXの方向性を定めます。
1. 業務プロセスの棚卸しと課題の特定
2. データ活用の要件定義
3. 現場との認識のすり合わせ
ステップ2:DX戦略の策定
ステップ1の要件定義に基づいて、それを実現するための技術とプロセス、各ステップをいつまでに、誰が、どのように実行するのか目標の設定をします。
1. 優先順位付け
2. 技術と業務プロセスの決定
・業務プロセスの再定義
3. 目標の設定
・効果測定指標の設定
ステップ3:実践と実行(PoC/スモールスタート)・KPIによる監視
戦略が整ったら、いよいよ具体的なDX施策を実行に移します。最初から大規模なプロジェクトを目指すのではなく、PoC(概念実証)やスモールスタートで小さく始め、成功体験を積み重ねることが重要です。
1. PoC(概念実証)の実施
2. スモールスタートとKPIによる測定
ステップ4:成功パターンの横展開と全体最適化
スモールスタートで成果が得られた成功パターンを、部門間を跨いで横展開していくことで、企業全体の最適化につながります。しかし実際は、テスト領域やスモールスタートでの部分最適の域を出ることは難しいです。そのため、最初から他の部門も使える仕様、横展開を見据えた仕組みを検討しておくことも必要です。 また、部分最適で終わらせないためには、現場を巻き込んだ全社的な意識の醸成と継続的な改善サイクルが鍵となります。
1. 成功事例の横展開と共有
2. 継続的な改善と技術のアップデート
DX推進のポイント・注意点
DX推進を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえ、陥りやすい落とし穴を避ける必要があります。
✓明確な目的設定
✓スモールスタートとアジャイルな推進
✓全社的なコミュニケーションと意識改革
✓既存システムの整理とデータ統合
✓セキュリティ対策の徹底
✓適切な外部パートナーの活用
実際のDX事例
DX推進は、業種や企業規模を問わず、様々な企業で成功事例が生まれています。ここでは、日本と海外のいくつかの最新のDX推進事例、atarayoの事例をご紹介します。
日本・海外の最新DX事例
■JAL:航空機メンテナンスの刷新
長年使用していた航空機のメンテナンス管理システムを刷新するために、IFS Cloudを導入。 航空機、エンジン、部品のメンテナンスを統合し、サプライチェーンや財務管理などの企業機能とも連携。これにより、メンテナンスの効率化やリアルタイム分析、予知保全が可能となり、航空機の稼働率を向上させることを目指しています。
参考:https://avitrader.com/2025/06/03/japan-airlines-to-modernise-aircraft-maintenance-with-ifs-cloud/
■LIXIL:顧客体験や従業員体験を向上を目的とした革新
AI音声認識を用いた接客サービスをオンラインショールームに導入し、顧客とのコミュニケーションをスムーズにしたり、3DやAR技術を活用し視覚化したリフォームサービスの提案を行う。また、生成AIツールの開発を通じて生産性向上を図るなど、全社的なDXの定着を目指しています。
参考:https://www.lixil.com/jp/investor/strategy/digital_index.html
■Acentra Health(米国):ヘルスケアの業務革新
特殊な医療文書を生成するWebアプリケーションMedScribeを開発し導入。MedScribeで生成された文書の承認率99%を達成し、対応時間の短縮、看護師の業務時間、コスト削減を実現。専門的な知識を要するヘルスケア分野でのAIを活用したDXは、業界全体から注目されており、今後の拡大が期待されています。
参考:https://www.microsoft.com/en/customers/story/19280-acentra-health-azure
atarayoのDX支援事例
■オンラインセミナー後の煩雑なデータ処理を自動化
課題: オンラインセミナーを主要施策とされているクライアント様企業にて、以下の課題を抱えていました。
- セミナー後の手作業でのデータ処理に膨大な時間と手間がかかり、本来取り組むべきセミナーの質向上や顧客対応の改善といった戦略的な業務に集中できていない。
- 入力ミスなどのヒューマンエラーが頻発している。
- フローが複雑になり、作業が属人化している。
支援・成果: ワンクリックでデータ整形から顧客管理システムへのインポートまで可能なデータ基盤を構築し、お客様が本来注力すべき顧客データを活かす”戦略に集中できる体制を作りました。結果として、人為的なミスを0にするとともに業務の大幅な効率化を実現しました。
■データ収集から整形、可視化までの自動化
課題: BtoBのマーケティング支援ツールを提供しているクライアント様企業にて、以下の課題を抱えていました。
- 複数の広告媒体を運用されており、散在する広告・サイト・MAツールのデータ集計とレポート作成に膨大な工数を費やし、肝心な施策の立案や改善施策の思考に時間が割けない。
- 手動でのデータ集計により、ヒューマンエラーが発生している。
支援・成果: データ収集基盤、データマート、LookerStudioによるダッシュボードを構築。散在したマーケティングデータの集計の自動化により作業工数を削減に加え、ヒューマンエラーがなくなり、データの精度が向上しました。また、自動化したことにより、戦略に十分な時間を取ることが可能になりました。
■広告の予算配分を最適化し、広告運用を最大化
課題: EC事業を展開するクライアント様企業にて、以下の課題を抱えていました。
- 広告予算の配分が過去の成功事例などの経験則に頼っており、根拠が曖昧な配分になっている。
- CPA(顧客獲得単価)が良好に見えるチャネルに予算を集中させた結果、全体的なCPAが悪化し、顧客獲得効率が低下する事態が発生していた。
- 複数の広告代理店が異なる媒体を担当していたため、広告効果の全体像を把握し、横断的に分析することが困難。
支援・成果: データ基盤を構築することで、散在していた広告データを統合、分析に適した形に整備。MMM分析により、各広告チャネルの貢献度とROIを可視化し、最適な予算配分をシミュレーションすることで、効果的な広告運用を提案しました。結果として、経験則から脱却し、機械学習を活用した最適な予算配分が可能となり、同じ広告予算で総コンバージョン数が1.3倍に増加しました。
まとめ
DXは企業が生き残り、未来を創造するために不可欠な変革です。少子高齢化、激化する競争、そして「2025年の崖」といった喫緊の課題に直面する今、データとデジタル技術を駆使したDX推進なくして企業の持続的な成長は望めません。 本記事で解説したロードマップとポイントを参考に、ぜひDX推進の一歩を踏み出してください。株式会社atarayoは、貴社のDXを力強く支援し、新たな価値創造を共に実現します。
よくあるご質問
Q1.DXは中小企業でも推進できますか?
A1. もちろん可能です。企業の規模を問わず、持続的な成長には不可欠な経営課題と言えます。特に、少子高齢化による人手不足の影響を受けやすい中小企業こそ、積極的にDXを推進していくべきです。
これまで、データを扱うには専門的な知識や技術が必要だとされてきましたが、これからはAIがデータインフラを構築する時代へと移行します。これにより、データインフラを基盤とした新たな価値創造へのハードルは劇的に低くなっています。AIだけでなく、IoTやクラウドコンピューティングといったデジタル技術も、近年では中小企業でも手軽に導入できるサービスとして普及が進んでいます。大規模な先行投資が困難な場合でも、まずは特定の業務プロセスをデジタル化する「スモールスタート」から始めることが成功への鍵となります。また、自社だけでの推進が難しい場合は、外部の専門パートナーの知見やノウハウを積極的に活用することが、効率的かつ確実なDX推進に繋がります。
Q2.どのような業界がDXを推進する必要がありますか?
A2.DXはあらゆる業界で有効であり、持続的な成長をするには不可欠です。 atarayoでは、業界を特に限定せず、データやAIを活用してビジネスを成長させたいという意欲のある企業様を支援しております。これまでには、BtoB SaaS・ITサービス、EC・通販、小売・店舗サービス、メディア、法律事務所、金融、教育、製造業など、幅広い業界でのご支援実績がございます。事例・実績についてはこちら(https://www.atarayo.co.jp/case-study/)。
Q3.DX推進の費用はどのくらいかかりますか?
A3. DX推進にかかる費用は、企業の規模、目指す変革の範囲、導入するデジタル技術の種類によって大きく異なります。初期投資としてシステムの導入費用やコンサルティング費用、継続的な運用・保守費用などが発生します。大切なのは、単なるコストとして捉えるのではなく、中長期的な視点で企業の新たな価値創造に繋がる「投資」と考えることです。まずはPoC(概念実証)やスモールスタートで小さく始め、効果を確認しながら段階的に投資を拡大していく方法が有効です。
Q4. DX推進の成果がなかなか見えません。どうすれば良いですか?
A4. DXの目的が曖昧だと、単にツール導入や短期的な効率化に留まり、本来のビジネス課題解決や価値創造に繋がらないケースがあります。また、適切なKPIが設定されていない、あるいは設定されていても測定が困難な場合は、その効果を数値で示しにくいこともあります。 成果を出すためには、以下の点が重要です。 まず、DXによって「何を解決したいのか」「どのような価値を創造したいのか」といった目的を明確にし、具体的な数値目標(KPI)を設定することが不可欠です。 次に、設定したKPIを定期的にモニタリングし、目標達成状況を確認しましょう。 投資したコストに対してどれだけの効果が得られたかを検証するため、ROI(投資収益率)の評価も行うべきです。最後に、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のPDCAサイクルを回し、常に最適化を図りながら継続的な改善を進めることが重要です。
Q5.DX推進の最初のステップである「要件定義」から相談することは可能ですか?
A5. はい、可能です。atarayoでは、分析要件定義から、データ収集基盤の構築、データ可視化、データを活用したマーケティング戦略の立案、施策支援までを一気通貫でサポートしています。パッケージ化されたサービスではなく、お客様の現状の課題や環境に合わせた柔軟な支援を提供していますので、まずはお気軽にご相談ください。