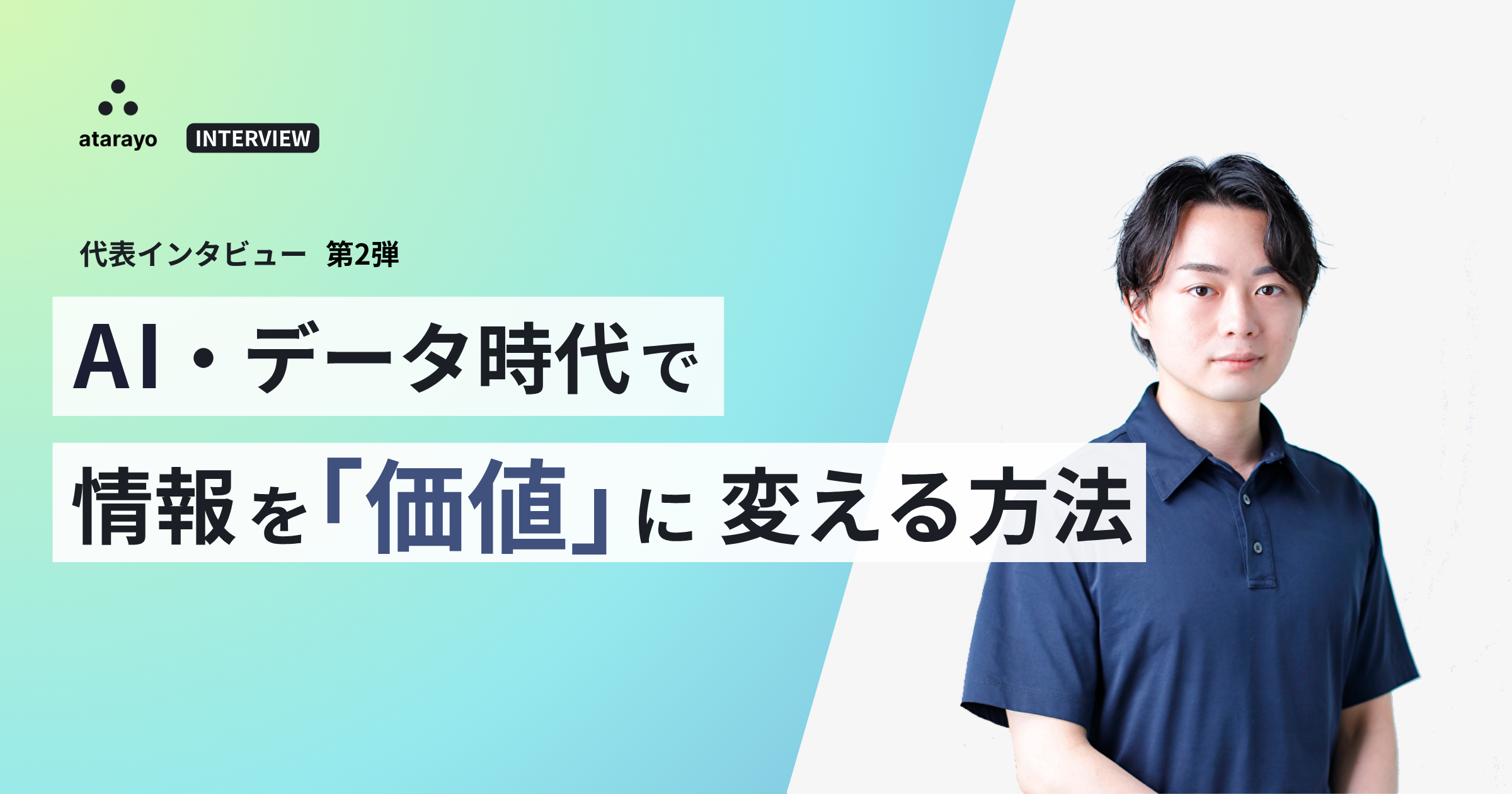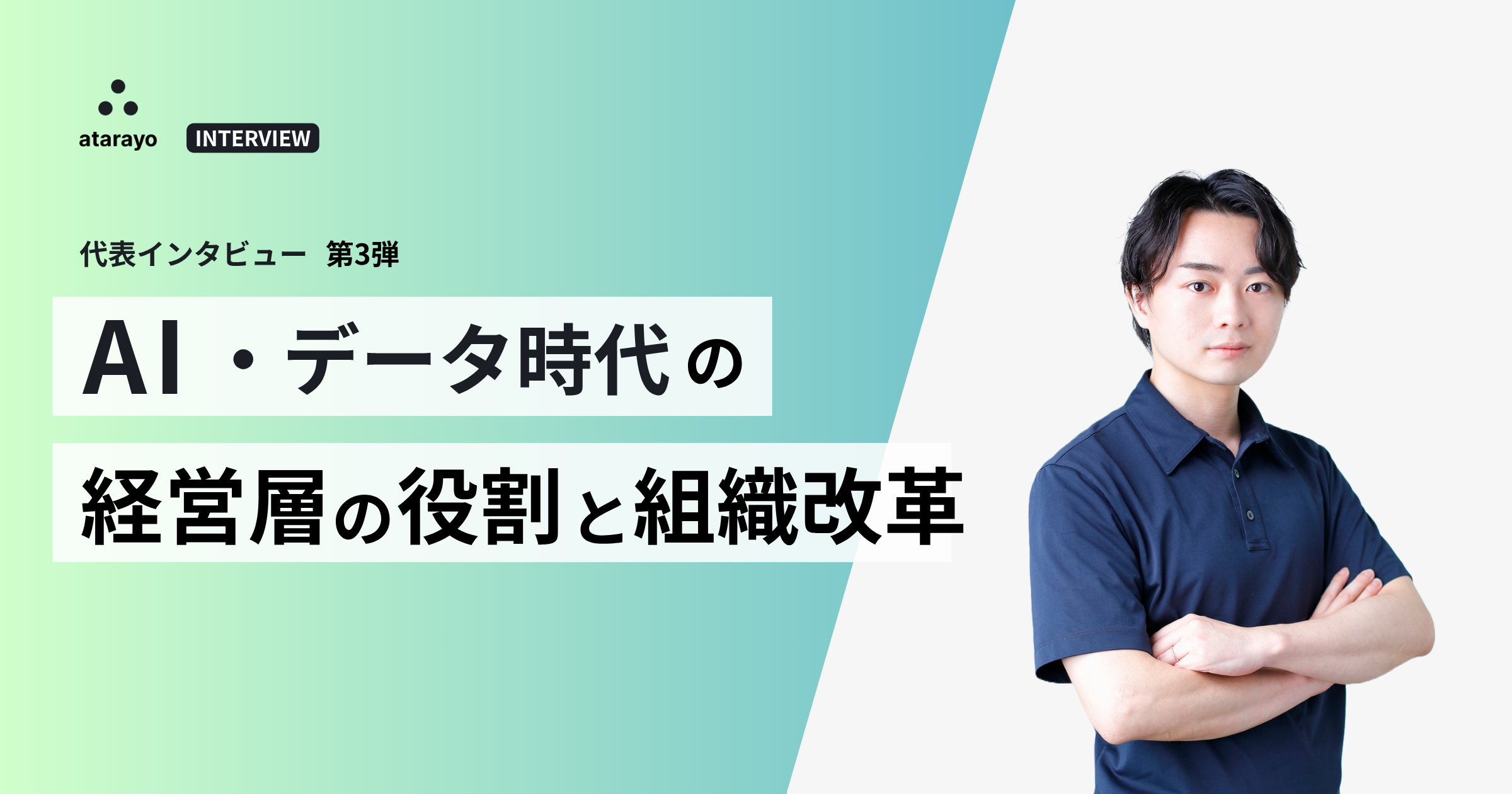AI×データ時代を勝ち抜く|中小企業におけるAI・データ活用の道筋
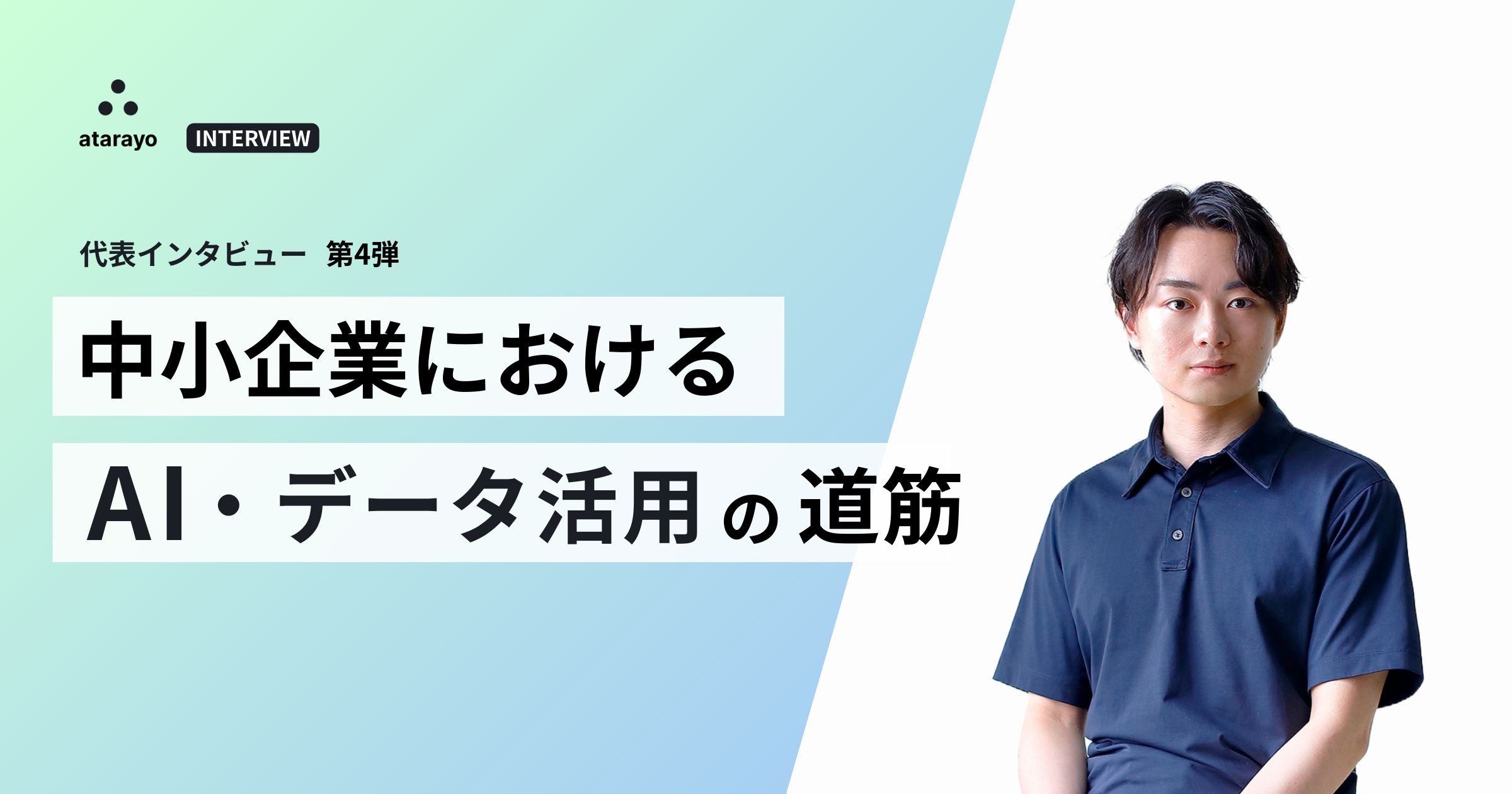
少子高齢化にともなう労働人口の減少、G7で最下位という生産性の低さなど、現代の企業は多くの課題に直面しています。特にリソースが限られている中小企業にとっては、事業の存続を左右しかねないほど深刻なものとなっています。課題を乗り越え、持続的に成長していくためには、AI・データを活用し、新たな活路を見出すことが求められています。
弊社代表取締役 加藤の視点から、「経営」という観点を通して、AIとデータの時代を勝ち抜くためのヒントをお聞きし、4つのテーマにわたりお届けしています。
今回はその第4弾として「AI×データ時代を勝ち抜く 中小企業における活用の道筋」についての考えをお届けします。
企業が直面する「データ」の壁とAI活用のハードル
日本の企業構造は中小企業が大半を占めており、少子高齢化の波は人手不足という形で直接的な影響を及ぼしています。これに加えて、依然としてDXの遅れが中小企業の成長を阻害する要因となっています。
これまでデータ活用は、データの収集から加工、分析、そして活用に至るまで、多岐にわたる専門性が求められ、多くの中小企業にとって自社だけでこれを完結させることは非常に困難なことでした。
しかし、AIの進化により、この状況は大きく変わりつつあります。
データ基盤が整備されていれば、複雑なプログラミングスキルやデータに関する深い知識がなくとも、AIを活用して仮説や潜在的な課題を洗い出したり、アウトプットを生成することができます。
さらに、普段話す言葉(自然言語)の指示で一定レベルまでの文章やコードを自動生成できるので、比較的容易にデータ活用を進めることが可能になります。
そのため、中小企業でも比較的容易にデータのインフラを構築し、新しい価値を創造するというハードルは格段に低くなっていくと思われます。これまで難しかったデータ活用が身近なものに変わる中で、企業は新たな成長のチャンスを掴み、社会への提供価値を高めていけるでしょう。
まずは「体験」から始めるAI導入と迅速な学習サイクルの確立
中小企業がデータ課題を克服し、AI活用を本格的に推進していくためには、段階的かつ実践的なステップを踏むことが重要です。
最も重要な第一歩は、実際にAIに触れてみて、その可能性を体感することです。例えば、生成AIツールを使ってメールの下書きを作成してみる、チャットボットツールで顧客対応のシミュレーションをしてみる、など、具体的なタスクにAIを適用してみることで、その利便性や効率性を肌で感じることができます。
何か新しいシステムを開発したり、大規模なプロジェクトを立ち上げる必要はありません。まずは既存の業務の一部にAIを取り入れ、実際に何かを作成したり、意思決定をサポートさせる経験を積むことが、AIへの理解を深め、社内での受容性を高める上で非常に有効です。
そして、AIツールの導入後は、とにかく迅速に学習サイクルを回していくことが必要です。一度導入したら終わりではなく、実際に運用しながら「どのような指示を与えればより良い結果が得られるか」「どの業務にAIが最もフィットするか」といった改善点を洗い出し、PDCAサイクルを回していくことがAI活用には不可欠なのです。
しかし、企業のAI導入には高い壁も存在します。多くのAI導入は、小規模なテスト段階で終わってしまい、本番環境への移行に至らないケースが非常に多いのが現状なのです。また、プロジェクトの失敗率に関して推定80%から85%と高く、ほとんどのAIへの投資が期待された成果を生み出せていないことを意味しています。
これは、技術の不足ではなく、ROIを度外視したAI導入やAI導入自体が目的化していること、部門間の連携不足など、ビジネス・組織面の課題が要因となっています。もちろん、まずはAIを体験することが第一歩です。しかしAI導入を失敗で終わらせないためには、明確な目的を設定し、全社的な取り組みを行うことが不可欠です。
現時点では、AIを使わない未来は無いと言えます。すでに、企業がAIを活用するかしないかのフェーズは過去のものとなっており、今は「どのようにAIを活用していくか」を最も優先して考え、行動すべきであると認識することが大切です。
「活用・実施」までを描くアプローチとパートナー選定の眼

中小企業が、限られたリソースの中でAI・データ活用を進めるには、企業の状況に合った現実的なアプローチと外部の力を借りる際の注意点を抑える必要があります。
まず、最も重視すべき点は、技術の導入だけで終わらせるのではなく、その先の「活用・実施」までを一貫して描くことです。単にデータを集めたり、AIツールを導入したりするだけでは、新たな価値は生まれません。「AIを活用して具体的に何を達成したいのか?」「どのようなビジネス課題を解決したいのか?」といった目的が明確であれば、それに合わせて必要なデータの定義や分析手法、AIの選定基準も定まります。
目的が不明確なまま、とりあえずAIを活用しても、見合う効果が得られず、時間とリソースの無駄になってしまうため、この要件定義は重要です。
また、外部の協力会社やコンサルタントの力を借りる際には、特に以下の3点を見極めることが大切です。
1. 「どうあるべきか」を共に考える姿勢と業界理解
データやAIを使う際には、「AIで何を成し遂げたいのかという明確なビジネス戦略が最も重要です。単に技術的なソリューションを提供するだけでなく、自社の市場、事業、そしてドメイン(業界知識)に対して深い理解を持ち、共に最適な「あるべき姿」を考え、学び、提案してくれるパートナーであるかを見極めてください。表面的なデータ分析スキルだけでなく、ビジネスの本質を理解し、自社の成長に貢献してくれるかどうかが重要です。
2. 事業を成長させるビジネス戦略
技術は導入して終わりではなく、重要なのは「その技術が、事業や実社会に活かせるか」、そして「具体的な意思決定や施策に繋げられるか」という点です。どんなに高度なAIや分析技術も、それを活用して何を成し遂げたいかという戦略がなければ意味をなしません。明確なビジネス戦略なしにとりあえず導入してみる、という姿勢ではROIが合わずに失敗してしまいます。そのため、ドメイン理解を前提として、「AIとデータを事業成長、業務効率化という目的に合わせて要件定義し、戦略を立てられるかどうか」という視点での選定が必要です。具体的には、ダッシュボードやAIツールを作って終わりではなく、それらを使ってどのように目的を達成するのかをストーリー立てて提案してくれるかどうかがポイントになるでしょう。
3. 全体像を描ける一気通貫での支援
多くの企業がAI・データ活用に失敗する原因の一つに、「データがサイロ化している」「実業務に組み込めない」といった問題があります。実際にAIを活用するには、データ基盤の準備とAIの構築、施策に組み込むことが必要です。そのため、AI、データ、施策の全てに対して理解があり、支援ができる企業であることが重要です。また、その上で「明確なビジネス戦略のもと、施策までを考慮して、AIの精度向上を支えるデータ基盤を構築できること」もパートナー選定における大事な指標になります。部分的な支援で終わるのではなく、全体像を描き、成果に繋がるまで一気通貫で伴走してくれるかどうかが大事な見極めポイントなのです。
中小企業がAIとデータを効果的に活用し、成長し続けるには、まず体験を通じてAIの可能性を理解すること、そして明確な目的を持って活用戦略を立てることが必要です。また、ビジネスの本質を理解し戦略を作り、具体的な施策まで共に伴走してくれるパートナーと組むことも重要な戦略となるでしょう。